「人材の活用」「従業員の教育」「人事制度」等について、事例満載の記事や専門知識が深まるコラム等を展開。自社の活性化や雇用管理のヒントに!
-

口下手の人のためのトークテクニック/桑山元
-

こころの守り方〜医療従事者のメンタルケアに学ぶ〜/吉村園子
-

ニュースPickUp
-

人が育つ会社/田中和彦
-

【現場に学ぶ】繁盛企業のマネジメント/岡本文宏
-

事例で考える困ったときのマネジメント対応/山田真由子
-

判例に学ぶ労使トラブルの処方箋/岡正俊
-

人事労務関連ワード辞典
-

マンガ・ワーママ人事課長キノコさん
-

ココロの座標/河田俊男
-

【企業に聞く】人が活きる組織
-

労働ニュースに思うこと
-

人材育成のツボ
-

シゴトの風景
「平均時給 の検索」「時給の平均や動向」等について、データを作成。労働市場の現状が分かります。
*一部記事の閲覧および機能をご利用いただくには、会員登録(無料)が必要です。会員登録はこちらアイデム人と仕事研究所では、「ビジネスマナーのブラッシュアップ」「新入社員の戦力化」「職種別・階層別の知識・スキルアップ」等につながるセミナーを開催しています。
- 研修開催一覧(東日本)
- 研修開催一覧(西日本)
- オーダーメイド研修
- オンライン研修アーカイブス
(動画研修) - セルフラーニング教材
(オンライン教材) - 研修の特徴
- 研修お申し込みの流れ
- 受講者の声
- 講師紹介
人材育成のツボ
- 人材育成のツボ一覧
- 「怒り」の奥にあるもの〜アンガーマネジメントが必要な理由〜
「怒り」の奥にあるもの〜アンガーマネジメントが必要な理由〜
アイデムの人材育成・研修部門の担当者が、日々の業務やお客さまとの対話から感じたことなどをつづります。(2025年8月7日)
責任感が強く、自分なりの「こうあるべき」という信念を大切にしている人ほど、理想が崩れたときに感情が爆発してしまうことがあります。それは、物事に真剣に向き合っているからこそ起こる反応であり、実はとても素直で誠実な一面を持っているのではないかと思います。だからこそ、自分が怒ってしまったことを後から悔やんだり、自分を責めてしまうことも少なくないようです。
「もう怒らないようにしよう」と思っても、感情をコントロールするのは難しいものです。私自身、アンガーマネジメントは「一度学べば終わり」ではなく、何度も繰り返し、自分の中に落とし込んでいくものだと感じています。怒りの扱い方を身につけるには、それなりの時間と訓練が必要です。焦らず、丁寧に向き合っていくことが、何よりも大切なのではないでしょうか。
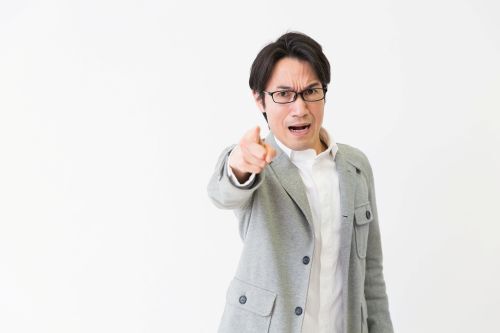
責任感の強いリーダー
職場に「忙しいから仕方がない」「私は間違っていない」といった言葉が漂うとき、あなたの職場にも“アンガーマネジメント”が必要なのかもしれません。実際にこんな声がありました。
その姿勢はチームにとって頼もしくもある一方、「厳しさ」に疲弊し、緊張感に包まれる日々が続いていました。周囲には「想定外のことが起きると一気に不機嫌になるのです」「パートの人たちには気を使ってくれている分、案件を持ってくる営業の人に言い過ぎていて心配です」といった声がありました。Aさんに対して「仕事ができるけど、ちょっと怖い人」という印象を抱き、言葉選びやタイミングにまで神経を使うようになっていたといいます。
アンガーマネジメントとは?
アンガーマネジメントとは、「怒らないようになること」ではありません。怒るべきことには上手に怒り、怒る必要のないことには振り回されない。つまり、怒りの感情をうまく扱うためのスキルです。
日本アンガーマネジメント協会によると、怒りのピークは「6秒間」といわれています。この6秒の間にどう対応するかが、関係性やその後の空気を大きく左右します。よく誤解されがちですが、アンガーマネジメントは感情を押し殺すことではありません。むしろ、怒りを抑えすぎると“爆発”するリスクが高くなることもあります。大切なのは、「自分の感情に気づき、理解し、適切に伝える」こと。怒りを否定するのではなく、適切に扱えるようになることがゴールなのです。
怒りは“氷山の一角”
怒りは、実は「第二次感情」とも呼ばれます。その奥には、不安・悲しみ・悔しさ・焦り・疲労などの“第一次感情”が隠れていることが多いのです。Aさんの怒りも、「間に合わせたいのに間に合わない」「もっと良くしたいのにできない」という焦りや「自分がやらなきゃいけない」というプレッシャーから来ていたのかもしれません。
●文/林原菜美(はやしはら なみ)
その他のコラム記事を見る
マンガ・ワーママ人事課長キノコさん
- [【第94回】数字の“裏”が重要!?採用に影響大な管理職比率&賃金差異公表義務拡大]
- 難しい労働関連の法律や、雇用や働き方に関する社会の動きなどを、親しみやすいマンガで分かりやすく解説します。
口下手の人のためのトークテクニック/桑山元
- [舐められない話し方とは?]
- わかりやすく話すためのテクニックや考え方、トークスキルを上げるヒントなどをお伝えします。
ニュースPickUp
- [2026年4月法改正・高年齢労働者の労災防止が努力義務化]
- 人事労務関連のニュースから、注目しておきたいものをピックアップしてお伝えします。


